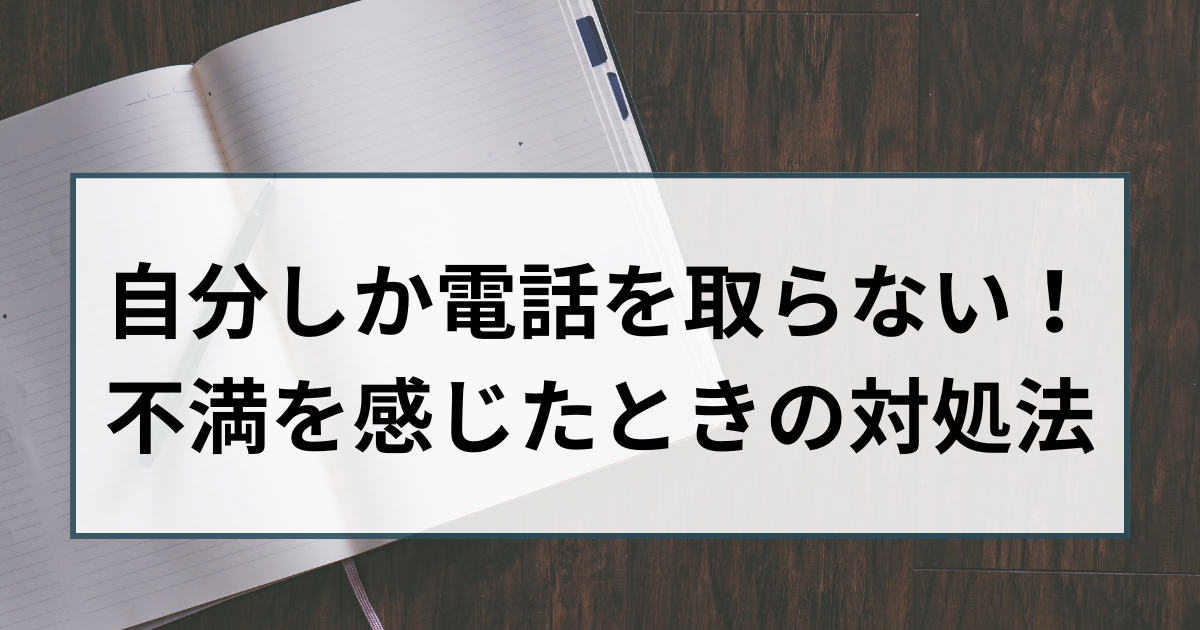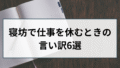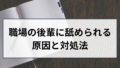「職場で電話を取るのが自分ばかり」そんなふうに感じたことはありませんか?
電話対応は本来、みんなで分担するべき業務のひとつです。
それなのに、気づけばいつも自分だけが反応していて、周りは知らん顔だと、不満やストレスがたまってしまいます。
この記事では、自分しか電話を取らないときに考えられる原因と、状況を改善するための具体的な対処法をご紹介します。

まじめに対応しているあなたが損をしないように、この記事を参考にしてみてください。
自分しか電話を取らない理由
「自分ばかりが電話を取っている」と感じるとき、その裏にはいくつかの理由がかくれています。
単に周りの人がさぼっている訳ではなく、無意識の思い込みや環境によって、偏りが生まれていることも多いです。
まずは、その原因を知ることが、解決の第一歩となります。
電話対応が自分の仕事と思われている
自分が電話を取ることが当たり前のように扱われていると、周りも「その人の仕事」と思い込んでしまうことがあります。
特に新人のころから電話に出る習慣があった場合、それが長く続くことで自然と役割として見なされてしまうのです。
そうなると、特別に何かを言わなくても「電話が鳴ったらあの人が取ってくれる」という空気ができあがり、他の人が動かなくなってしまいます。
このような状況が起きるのは、以下の要因が考えられます。
- 入社当初から電話を率先して取っていた
- 他の人があまり反応しない職場の雰囲気がある
- 業務分担がはっきりしていない

無意識のうちに「固定された役割」ができあがっているケースです。
周りが電話に気づかない
周りの人が電話に出ない理由として、そもそも着信に気づいていない可能性もあります。
本人に悪気があるわけではなく、物理的に音が聞こえなかったり、集中していて電話の存在に気づけなかったりする場合です。
集中して作業をしていると、周囲の音が耳に入らないこともありますし、ヘッドホンなどで遮音されている場合はなおさらです。
このようなケースには次のような背景があるかもしれません。
- 電話の音が小さく設定されている
- 会話や作業で気づきにくい状況にある
- 一部の人が電話に対する意識が低い

誰が悪いという話ではなく、職場の環境が原因となっていることもあります。
電話を取りたくない人がいる
中には、意識的に電話を取らないようにしている人もいます。
「電話対応に対して苦手意識がある」「作業を中断したくない」など、個人の気持ちが関係していることも少なくありません。
こうした態度が習慣化してしまうと、まじめに対応している人に負担が偏りやすくなります。
そして、やがて「誰も取らないから自分が取るしかない」と感じる悪循環につながってしまいます。
考えられる背景としては以下のようなものがあります。
- 電話に苦手意識がある人が多い
- 忙しさを理由に対応を後まわしにしている
- 「誰かがやるだろう」という甘えがある

気づかぬうちに責任の押しつけ合いになっている職場もあるかもしれません。
自分しか電話を取らないときの対処法
電話対応の負担をひとりで抱えてしまう状況を変えるためには、具体的な行動が必要です。
伝え方を工夫したり、仕組みを見直したりすることで、少しずつ改善することができます。
ここでは、実際に役立つ対処法をご紹介します。
電話に出られないこともあるとアピールする
電話をすべて自分が取ってしまうと、周囲は「任せても大丈夫」と思い込んでしまいます。
そのため、あえて「今は対応できない」という姿勢を見せることも大切です。
以下のような工夫が役立ちます。
- 作業に集中しているときは、あえてすぐに取らない
- 席をはずす時間をつくる
- 他の人の様子を見る余裕をもつ

「自分だけがやる必要はない」という雰囲気を出すことで、自然と周囲の行動も変わってくることがあります。
電話当番を決めるよう提案する
電話を取る人が偏らないようにするには、仕組みを作るのが有効です。
「今日は〇〇さん」「午後は〇〇さん」など、当番制を取り入れると公平になります。
提案の仕方としては、以下の通りです。
- 「電話の負担が分かれると助かります」
- 「曜日や時間で分けるのはどうでしょう」
- 「今の状況だと偏っている気がします」
このように丁寧な言い回しを心がければ、協力を得られやすくなります。

みんなで電話を取る仕組みをつくることが、負担の軽減につながります。
ルールを再確認する
職場によっては、「電話は気づいた人が取る」という暗黙のルールがあるかもしれません。
そのルールが守られていない場合、改めて確認することが必要です。
具体的な行動としては、以下の通りです。
- 取り決めを明確にするよう相談する
- チーム内で一度話し合いの機会をつくる
- ルールを守ろうと提案する

ルールを共有しなおすことで、電話対応への意識が全員に行きわたります。
上司に偏りを相談する
電話対応の負担が明らかに偏っている場合は、自分ひとりで抱え込まず、上司に相談することが大切です。
上司は全体の業務のバランスを見る立場なので、気づいていないこともあるのです。
相談の際に意識したいポイントは、以下のとおりです。
- 「業務に集中できないことが増えています」と伝える
- 「電話対応のバランスについて、一度見直していただけますか?」と話す
- 記録があれば一緒に見せる

責めるのではなく、「改善の相談」という形で持ちかけることで、協力を得やすくなります。
電話対応マニュアルを整備する
電話対応の方法が人によってバラバラだと、苦手意識を持つ人が増えてしまいがちです。
特に新人は、電話対応に不安を持っています。
そこで、職場として誰でも対応しやすくなるよう、マニュアルを整えることが効果的です。
マニュアルに盛り込むとよい内容は次の通りです。
- 電話の取り方・対応の基本
- 用件をメモするときの書き方
- よくある質問への答え方の例
こうした内容を共有することで、「自分にもできる」と思える人が増え、電話対応への協力を得やすくなります。

負担を分け合える環境づくりの一歩となるでしょう。
まとめ:電話対応の負担は分け合うもの
職場で自分しか電話を取っていないと感じたとき、そのままにしておくと不満がたまり、仕事への意欲も下がってしまいます。
しかし、正しい対処をすれば、その状況を少しずつ改善することはできます。
本記事で紹介した対処法は、以下の通りです。
- 電話に出られないこともあるとアピールする
- 電話当番を決めるよう提案する
- ルールを再確認する
- 上司に偏りを相談する
- 電話対応マニュアルを整備する
このような工夫を重ねることで、電話対応の偏りを解消し、みんなが気持ちよく働ける環境に近づけます。
自分を守りつつ、周囲との協力も大切にしていきましょう。